
【モノグサPdMシリーズ vol.10】モノグサのCSとPdMの視点
こんにちは、モノグサでProduct Managerをしている伊藤卓(すぐる)です。
シリーズのVol.4でも触れましたが、私は2021年4月入社時点ではCustomer Success(以下、CS)で、その後2022年末頃にProduct Manager(以下、PdM)に異動しています。
※ちなみに本業はPdMのままですが、2023年4月からはEscalation Engineerというポジションのマネージャーもしています。
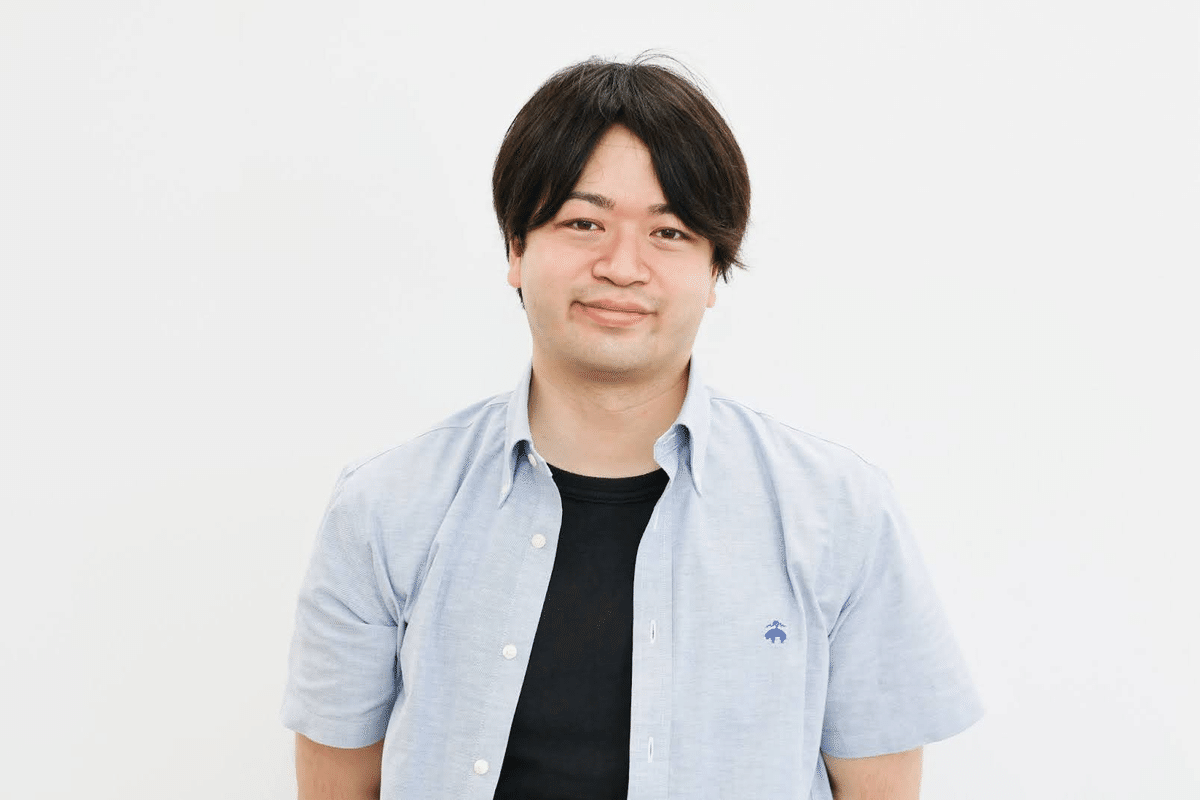
今となっては相対的に古株になってきたこともあり、様々な職種の方とカジュアル面談や選考でお会いすることも多くなってきているのですが、その中で「Business職とProduct職の違いはどのように感じますか?」という、両職種経験しているからこその質問をいただくことがあります。
その方のご興味や応募職種などに応じて様々なことをお答えしてきましたが、異動して1年半経つ中で、改めてこれまで感じてきたCSとPdMの視点の違いを振り返ってみたいと思います。
目指す「成功」
まず、それぞれの職種は何を成功と捉えているのでしょうか。一般的(?)には、CSは「顧客」の成功を担い、PdMは「プロダクト」の成功を担っていると思います。
最終的にはどのような職種でも顧客への価値提供を目指すべき、というのはありつつ、基本的にはモノグサも同様の視点があります。
その上で、「顧客」はどの属性(塾、学校、企業等)のどの顧客なのか、「プロダクト」であればどの開発領域なのか、という担当があります。
成功を実現するために、CSは担当顧客のことを深く知り、様々な施策を講ずることになります。その施策のインプットとしてプロダクトの機能を広く知ったり、施策の結果として顧客の声を社内にフィードバックすることになります。
一方でPdMは、基本的には担当する開発領域に存在する課題を深く理解し、(担当領域)プロダクトの成功のために様々なプロジェクト(機能開発)をリードします。特定の顧客に限らず、顧客属性を横断して課題を検討することになり、必然的に顧客を広く知ることになります。(とはいえ、場合によっては担当以外の開発領域についても広く検討したり、特定属性に寄って検討することもあります)
私自身、CS時代には開発領域によらず(というよりも開発領域というものをあまり意識せず) 様々な機能に触れ、顧客に応じてそれらを組み合わせて運用提案などを行っていたり、どうしても課題がありそうであれば開発課題・要望の起票などをしていました。
PdMになった今は、必然的に自分が担当する領域の課題や機能、その優先度が思考の中心になり、顧客の声を把握するにしても、特定の顧客というよりは、多くの顧客でも同様のニーズはあるか、その深刻さはどの程度なのか(≒課題の広さや深さはどうか)、を重視するようになってきています。
課題解決の方法:機能開発と運用

それぞれの「成功」を目指し、顧客の課題を解決する、もしくはMonoxerの導入効果を創出するにあたっては、大きく「機能開発」と「運用(設計)」の2つの方法があると思います。
PdMがメインで関わることになる機能開発においては、今存在しない機能を作り出すことで、これまでリーチできていなかった課題を解決することになります。また、MonoxerはSaaSとしてサービス提供していることもあり、基本的に個社専用の機能開発というよりは、より広い顧客に、よりインパクトのある課題解決が出来る方法を模索し、実装しています。
機能がリリースされ、実際に顧客に利用されることは、一つのマイルストーンを越えたことになり、とても達成感のあることです。
同時に、機能開発にあたって立てていた仮説の答え合わせにもなるので緊張感のあることでもあるのですが、どのような形であれ、実際に機能を利用した顧客からのフィードバックはとても貴重なものです。 (もちろん喜びの声も嬉しいのですが、さらなる改善要望も非常にありがたいものです。)
CSがメインで関わることになる、Monoxerを使って効果をどのように出すかの運用(設計)においては、基本的に機能は所与のものとなります。その中で、顧客の目標を一緒に検討し、それに対してどのような運用設計が必要で、今ある機能をどのように活用していくのか、を組み立てていくのがモノグサCSの難しさでもあり、同時に大きな醍醐味でもあります。塾、学校、社会人などの領域それぞれで運用のあり方は異なりますし、もちろん領域の中でも顧客によって目標が異なれば運用の仕方も多様なものになり、絶対的なやり方というものは存在しません。
顧客の協力もいただきながらMonoxerを運用し、実際に効果が得られる(先生や生徒から喜びの声をいただける)ことは、何ものにも代えがたい達成感や嬉しさを感じるものだと思います。
ただ、醍醐味だからこそ、“運用”という名のもとに少し無理をしてしまっているケースもあると、Product側の立場になってみると感じることはあります。そのあたりは元CSとしても上手く拾い、CSがより楽に、より高い価値を顧客に届けられるような機能開発をしていければなと思います。
(これは私の反省でもありますが、スケジュールを引いた際に「その時期の顧客は定期テストがあり難しい」と、とあるCSの方に言われたことがあり、「CSの頃なら当然のように分かっていたのに、ここまで現場意識が下がってしまっていたか....」と反省しました)
Product Roadmap, あるいはBusiness Roadmap
ここまで書いてきたことは役割分担でもあるのでそれ自体に良い悪いも無いと思いますし、もちろん真に顧客やプロダクトの成功を実現するにはそれらの担当を超えて動くべきですが、顧客を見据えるか、プロダクトを見据えるか、それぞれにそれぞれ特有の面白さがあると思います。
ここまでのPdMシリーズを読まれた方にはモノグサのPdMの面白さは重々伝わっていると思いますが、一緒にプロジェクトを行うことになるCSなどのBusiness職も非常に素晴らしい方々ばかりで、そういった意味での面白さ、刺激にも満ち溢れていると思います。
以下は「プロダクト・レッド・オーガニゼーション」という本の一節ですが、まさにモノグサのBusiness(CS)メンバーが体現できていることだと思います。
競争力の維持は、効果的で変化に強いカスタマーサクセスチームにますます依存するようになっている。カスタマーサクセスはプロダクト主導型組織の目であり、耳であり、心でもある。カスタマーサクセスチームは、最前線で顧客に目を光らせ、耳を傾け、顧客が価値を見出すのを支援する。(中略)顧客の健全度や幸福度を事実となるデータで計測・監視し、顧客のニーズを企業全体に伝えられるのだ。
モノグサでは現在も様々なプロジェクトが進行しており、その中でBusinessとProductが双方を尊重しながらよく連携できていると日々感じます。
PdMがProduct Roadmapを描くとき、机上の空論にならないようにBusinessに顧客の状況をヒアリングすることは多々ありますし、
CSからも各顧客のN=1を集約し、一定整理したうえでProductに連携することで、新しい機能開発を生み出す事業開発が実現できているのではと感じます。
またBusiness側ではBusiness Roadmap(通称BizRDM)という事業開発の仕組みがあります。課題を点として捉えるのではなく、それらを集約・抽象化し、一つのテーマやプロジェクト(テーマの下に複数のプロジェクトが紐づく構造)として扱い、その単位でBusiness側で優先度を付けています。また、Productにはテーマやプロジェクト単位で課題を接続しており、単発的な課題解決や機能開発ではなく、より大きい目線で最適な課題解決を目指せるようになっています。
顧客の解像度については、PdMも商談に同席することで顧客と直接会話出来る機会も(ありがたいことに)多くあります。ただ、真にリアルを感じるのはちょっとした打合せや、顧客との電話・メール、訪問した際の教室の雰囲気など、細部にあるとも感じます。そういうリアルをBusinessからProductに伝えていただくことが、プロダクトの成功、ひいては顧客の成功につながると思っています。
Salesの文脈で語ったものですが、Business長でもあるCEO竹内が考える事業開発とは何か、については以下もご覧ください。
“事業開発”には様々な意味が込められていますが、Productとの連携においては「自分の課題解決能力をプロダクトの価値向上に使う」という表現がしっくりくる気がします。
最後に
いかがでしたでしょうか。あくまでも私の目線ではありますが、モノグサPdMはどのような視点で働いていて、どのようなBizメンバーと関わるのかを少しでも共有できたなら幸いです。
ちなみにもう少し俯瞰的な目線での、開発プロセス全体における様々な職種との役割分担は、vol.4の記事で書いておりますのでご興味あればぜひご覧ください。
また、本文では違いに注目しましたが、BizとProduct、またCorp、HRとも共通していることが多くあると感じています。
以下は一例ですが、こういう目線を共有できているからこそ、お互いによく連携できているのだと思います。
「記憶を日常に。」のミッションに共感し、実現を目指している
顧客への提供価値を重要な判断軸として考えている(実業務での距離感の違いはあれど)
これまでの知見をフル動員、かつ更にアップデートしながら業務している(総合格闘技感)
立場によらずオープンに議論し、出てきた意見を基に解決策の質の向上を目指している

モノグサでは私たちと一緒に働くPdMやCSなど様々な職種を絶賛募集中です。モノグサに興味を持った方はぜひ下記からカジュアル面談等にお申し込みください!お待ちしてます!
↓↓↓

